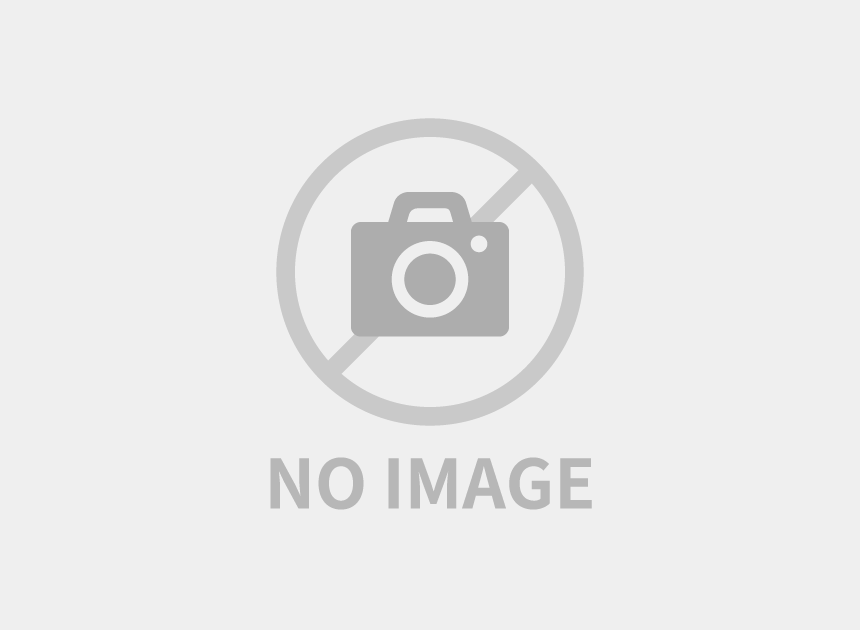城東小日記
自らを切り拓く子 -明るい心 進んで勉強 強いからだ-
-
教育シンポジウム「ふるさとの絆 未来に託す夢と希望」
- 公開日
- 2012/10/31
- 更新日
- 2012/10/31
校長室より
先日、教育シンポジウムに参加する機会に恵まれ大きな示唆を受けました。私が心に残...
-
-
-
-
親子観劇会「走れ!メロス」(10月20日)
- 公開日
- 2012/10/25
- 更新日
- 2012/10/25
校長室より
20日(土)に実施した学校公開に、多くの保護者の皆様に来ていただき嬉しく思いま...
-
-
-
授業参観と親子観劇会 (10月20日(土))【予告】
- 公開日
- 2012/10/17
- 更新日
- 2012/10/17
校長室より
すでにお知らせしたとおり今週の土曜日に学校公開を行います。授業参観に合わせ、京...
-
-