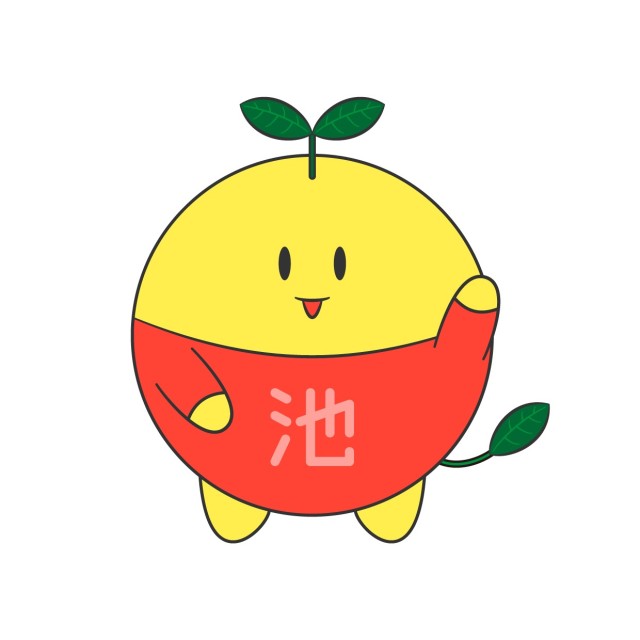アフターコロナのその先に
- 公開日
- 2020/05/27
- 更新日
- 2020/05/27
桜下村塾
かつて1950年代には「ガチャマン(ガチャンと織れば1万円もうかる)景気」があり、繊維産業が栄えました。その後1960年代には、鉄鋼・化学・電力など素材産業が設備投資をすすめ、池田勇人内閣の「所得倍増計画」とともに国民所得も増え、各家庭にはテレビ・冷蔵庫・洗濯機のいわゆる「三種の神器」が普及することになります。1970年代に向けて、鉄鋼・電気製品の輸出が増大し、日本は高度経済成長期へと突入していきました。
様々な時代に様々な産業が勃興し、景気の良い業界に人材が集まることになりました。しかし時代の変遷とともに景気は変動し、将来を見据え希望の業種に就職できたとしても、それで一生安泰とならないところが現代の就活の難しいところです。
昨今のコロナ禍も、これまで景気が良く、学生にとって有利な状況が一転して、景気の悪化に伴い、内定取り消しや求人数の削減など就活をすすめる学生にとって大きな悩みとなっています。
かつて日本は、幕末期と第二次大戦という二度に渡る国家存亡の危機を乗り越え、その後不死鳥のように国際舞台に復活しました。今回のコロナ禍も、なんとか糸口をみつけて、復興せねばなりません。ただし、コロナ禍以前と同様の経済や生活を求めても、早急には無理でしょう。それよりも、これを機に、新たな生活様式や、経済観、幸福観、就職観を持つべきではないでしょうか。
学習の遅れが不安で9月入学を議論するよりも、コロナ禍で「ステイホーム」や「家庭学習」を強いられ、我慢に我慢を重ね、生きぬ抜いてくれた子ども達に、例年以上に「今年の学校は良かった。」と、後々語り草にしてもらえるような思い出づくりや体験をさせてあげられないかと感じています。もちろん、3密を避け、ソーシャルディスタンスを確保することは必須条件ですが…。
例えば、仕事をなくした多くの役者さん達に全国の小中学校に出向いてもらい、子ども達に本物の総合芸術「演劇」を間近で観てもらう「ギガスクール構想」ならぬ「生スクール構想」なんてどうでしょう。もちろん、ウイルスの第二波襲来に備えてオンライン授業の準備も必要ではありますが、こんなにも人との接触を避けねばならなかった3ヶ月間は、大戦中を除いてこれまでになかったことです。今、子ども達が求めているのは、直に鑑賞し感動できる「実体験」を伴う学習なのではないでしょうか。
過ぎてしまった時間を戻すことはできませんが、残された時間をより充実したものに、良い思い出にすることは可能だと思います。残された時間も予算も有限ですが、その活用の仕方は無限の可能性を秘めています。「ピンチは最大のチャンス」のはずです。全ての教育に携わる人々の知恵と勇気と胆力にご期待ください。教育は「国家100年の計」です。疫病の流行で揺るぎはしません。