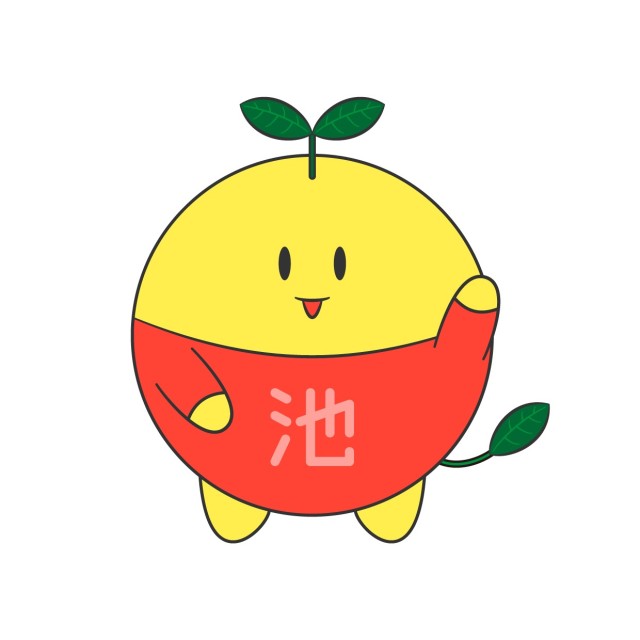最後は「人」で決まる
- 公開日
- 2021/08/03
- 更新日
- 2021/08/03
桜下村塾
組織に集う「人」こそが、最も重要で、ピンチの時こそ、力があって、決断し、行動できる人材が、どれほどいるかが勝負を決する鍵となる。
武田信玄は、甲斐国(現在の山梨県)を治めた戦国大名です。中央政権との交渉もあったことから、和歌の教養をたしなんでいました。彼の詠んだ有名な和歌には、「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇(あだ)は敵なり」という一首があります。和歌の意味は読んで字のごとく、人は城のようなものであり、人は石垣のようなものであり、人は堀のようなものである、と「人」の重要性を説いています。
多くの戦国武将が堅牢な城を持つなかで、武田信玄は城を築くことなく、防御力が決して高いとは言えない躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)を拠点としました。
武田信玄が城を持たなかった理由としては、山々に囲まれ、天然の要害となっている甲斐国の地形もあり、また、彼の和歌で詠まれているように、城や石垣や堀以上に、なによりも重要なのは「人」である、と考えたことにあると思います。立派な城を築くよりも、強い武士を育て、戦う集団を作ることの方が大切だと考えたからでしょう。
戦国最強と謳われた信玄の強さの秘訣は、彼の「人」に対する「思い」にあり。